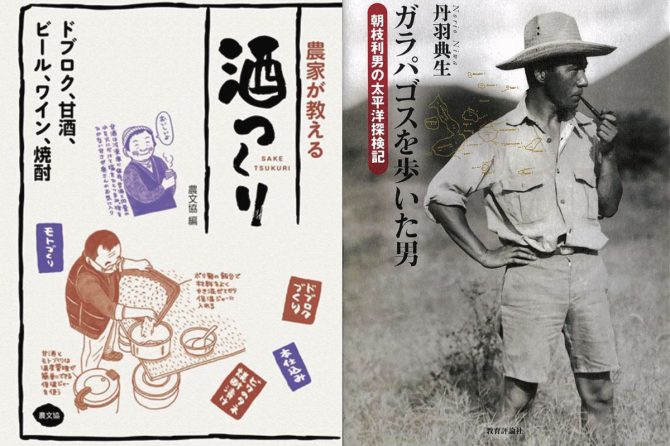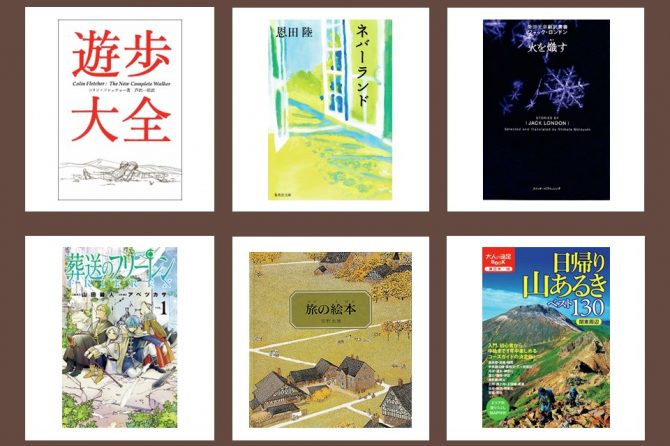本記事は、BE-PAL2024年12月号にて掲載された内容の、ロングインタビュー編です。
低山藪山が舞台のサラリーマンの休日登山から、人間の本質に迫って山岳文学の新境地を拓く

『バリ山行』の「バリ」とは「バリエーション(=変化・変型・変種)」のことだ。すでに誰かが切り拓いているルートからはずれ、道のない山域を行く登山である。登山に「冒険」を求める者たちが志向する世界。その物語がヒマラヤ山脈の高山でもなければ、アルプス山脈の難壁でもないのだ。神戸市からほど近い六甲山系が舞台である。『バリ山行』の作者、松永K三蔵さんとお会いしたのはその一角。森の中に座り込んで話を聞いた。
「自分が書けるのは、本当に身近な人であり山だと思いました」
「育ったのが西宮ですから六甲の麓といっていいようなところです。でも、登山は5年ほど前に始めました。いわゆる山岳小説、あるいは登山家の山行記をずっと読んできたというわけでもないんです。六甲で育った登山家、加藤文太郎(1905〜36)を描いた新田次郎の『孤高の人』は、本好きの義母から勧められて読みました。山を題材に書いてみようかなと思って、山岳小説をいくつか読んだ方がいいのかとも考えましたが、いや、自分の感覚でそのまま書こうと考え直しました」
森は巨木が生い茂るわけではないが、鬱蒼としていた。トレイルは確かにあるが、藪に覆われているところもあり、あっ人影かと目を凝らしていると、しばらくして登山者が全身を現したりする。
「エキスパートというか、達人のよう登山家を主人公にする物語もありますが、僕自身がエキスパートではありません。であれば、自分が書けるのは、本当に身近な人であり山だと思いました。そして、親しんできた六甲山系という舞台設定にしました」
どこにでもありそうな日常である。それを登山と同列に書く
六甲山系は東西に長く、全長は約52km。1000mを超えることはないが、起伏に富んでいる。岩場もあって、そこでは歴史上、何人もの登山家が育ち、彼らはヒマラヤやアルプスへと旅立った。低山といっても登山史上にしっかり名を残す地で、神戸の街から近いこともあって登山者を魅了し続けている。北へ抜ければ有馬温泉。縦横にトレイルが拓かれている。『バリ山行』では、こうした低山登山の聖地でも、少しトレイルからはずれると道迷い、その果ての滑落などの危険が待ち構え、場合によって命を落としかねないことを教える。低山藪山は充分に冒険物語が編める場所だと気づかせてくれる点で、松永さんの作品は山岳文学の新境地を拓いたといえるだろう。
もうひとつ、描かれている山行が、会社員の休日登山というのも『バリ山行』を特徴付けている。建物の外装修繕を専門に会社での出来事が濃密に綴られているのだ。主人公は内装リフォーム会社から転職して2年目で、保険会社に勤める妻と幼子がひとり。前の会社では仕事以外で社員と付き合うことを避けてきたのを反省し、誘われるままに会社の同僚たちと休日に六甲山系へ行く。モチベーションも単純で「山頂でカップラーメンを食べたい」だ。主人公にとって、そんな登山は楽しく、また以前と変わり始めたことを妻も喜ぶ。どこにでもありそうな日常である。それを登山と同列に書く。文学は異端の人生を描くことだけで成立するのではないのだ。そこが、自身も会社員の「兼業作家」の松永さんの真骨頂である。
「たとえばエベレストにチャレンジするような登山家でも、純粋に登山だけされているわけではないですよね。街で遠征に協力してくれる支援者を募ったりしています。登山を成り立たせるために仕事がある。登山は仕事と無縁であるわけじゃないですよね。僕も山に来ても仕事のことをいろいろ考えますし、仕事のこともしっかり書いた方がリアルに違いないと思いました」

「僕自身は、どちらかといえば主人公に近いと思います」
作中の会社に、ひとり変わり者がいる。それが妻鹿という男だ。仕事で社内の人間と組むことほとんどない。営業が本務だが特殊な修繕も見抜けるような技能も持っている。そんな妻鹿がバリの実践者だ。社内にできた登山サークルの活動には興味なさそうである。それでも、妻鹿は誘いに乗って一度だけサークルの山行に参加する。山中の分かりやすいとはいえない場所を指定し、そこに現れた彼の姿にみんな驚く。サークルのメンバーは、主人公を含めて思い思いにアウトドア・ブランドのウエアで装っていたのだが、妻鹿はホームセンターで揃えた安っぽいウエアでノコギリや鉈を持っていたのだ。
やがて会社は、それまでの発注先を直に求めていく営業から、大会社の下請けに経営方針を転換。妻鹿は会社の方針に背くように古くからやり方で仕事を続ける。そのうち、目論見どおりには業績は上がらず社内にリストラの噂が立つが、妻鹿はリストラ筆頭候補かもしれないのにどこ吹く風だ。主人公は会社の動向に右往左往しつつ、次第に妻鹿が気になり始め、ついにバリへの同行を申し出る。ひとりがいい妻鹿も何を思ったか同意した。
バリは、トレイルを歩く登山とは別世界だった。藪を切り払って道をつくり、ザイルを使って谷へ下りたかと思えば、今度はザイルを上部の木に固定して登っていく。スマホに落とし込んだ地図アプリが手掛かりだ。難所を越えても絶景が待っているわけではない。トレイルから逸れて車道に出るまでのことである。
だんだん主人公は、これのどこが楽しいのだという気持ちになってくる。そして、派手に滑落。幸い木に引っかかって最悪の事態は免れたが、足を捻挫し、一張羅のような高級ウエアはボロボロになる。そんな姿の主人公に妻鹿がいう。「ね、感じるでしょ?」。生の実感を問うたのだ。それに主人公は「感じませんよ!」と猛烈に反発。さらに会社での妻鹿の様子にたまっていた鬱憤が爆発させる。「本物の危険は山じゃないですよ。街ですよ! 生活ですよ。妻鹿さんはそれから逃げてるだけじゃないですか! ズルくないですか? 不安から目を逸らして、山は、バリは刺激的ですけど、いや“本物”って、刺激的なもんじゃなく、もっと当たり前の日常にあるもんじゃないですか。」
作中でふたりにそんなやりとりをさせた思いは何か
「僕自身は、どちらかと言えば主人公に近いと思います。小さなことでも不安になって、いろいろと考えてしまいます。誰しもが秘かに突き抜けたいと思うような、妻鹿的な要素も持っている。一方で、そんなことはできないだろうっていう気持ちもある。冒険ということへの憧憬と反撥ですね。社会のルールやシステムというものは、揶揄されがちで、そういうものからドロップアウトしていくというのは挑戦的でヒロイックで魅力的ですが、実は現実はそれほど甘くない」
作中では、主人公とのバリの直後に妻鹿に転機が訪れる。「妻鹿はどうなるのか。じつは僕にもわからないですよ」と松永さん。やがて主人公は登山サークルとは距離を置き始め、ついにホームセンターで安物のウエアを揃え、再びバリに行く。
安全と思える日常のすぐ近くに危険は潜む。それをリアルに知られる力が『バリ山行』にはあるのだ。安定した道を行くかイバラの道とわかりながら冒険するか、登山家でもなく冒険家でなくても日々の暮らしで誰もが迷っている。生きることそのものが両極の間で揺れ動くことなのではないか。本当に挑戦者の対極は臆病者なのだろうか。『バリ山行』は、登山を超越して根源的な問いを想起させる作品なのだ。
平野啓一郎さんは選評の最後にこう締めくくった
芥川賞選考委員のひとり、平野啓一郎さんは選評をこう締めくくった。「文学的な実験性という点では、物足りなさもあるが、この完成度は立派であり、多くの読者に愛される作品であろう」。『バリ山行』は平易な文体で綴られている。難解ではなく、確かに純文学にある実験性は薄いのかもしれない。ただ、それは松永さんという作家が「オモロイ純文」を標榜するからだ。文学的実験がもたらす難解さとは対極のところに身を置いているのだ。そんな松永さんは「登山と文学は親和性が高い」といった。
「小説を書いているときは没我状態になります。山をひとりで歩いているときも、結構それに近い感じなんですよ。オモロイといっても凡庸な言葉はできるだけ避けたい。山を歩いているとき、ピュアなええ言葉が、ふっと降りてくるような感覚があります。それは快感ですね。自然の中で自分と向き合っているときは、たぶん、根源的なものにかなり近くまでアプローチできているんだろうなと思います。その感覚は大切だとも思います」
今後も松永さんは登山を題材にした作品を描くだろうか? 必ずしもそうならないという予感はする。しかし、たとえ登山を描かなくても、山を歩くことはやめない作家なのではないか。自作がどうなるか、本当に楽しみである。
インタビュアー:藍野裕之 写真:安田健示