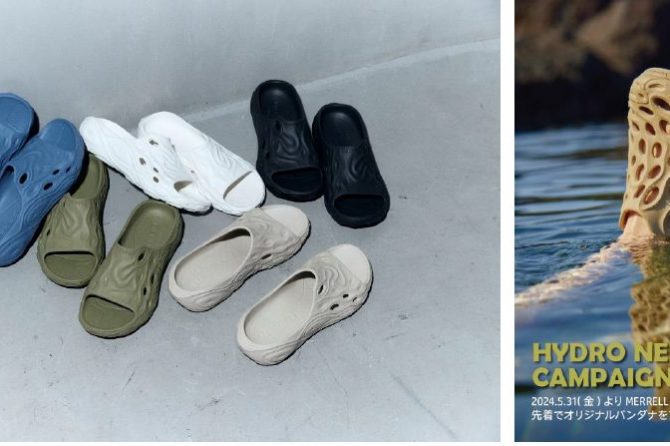NODATEシリーズで知られる関美工堂を訪れ、漆器を取り巻く環境と魅力を教えてもらった。
アウトドアでも使える漆器シリーズ「NODATE」とは?

「砂の上にNODATE Mugを置いて写真を撮ったら”漆器をそんな風に扱うんじゃない”と職人から叱られました。でも、漆器は酸やアルカリに強く、抗菌性があります。おまけに軽くて割れにくい。氷点下でも凍り付かないなどアウトドアシーンで求められる性能を備えているんです。
光沢のある磨き上げた漆塗りの食器は工芸品と言いますか、特別な日に使うモノですが、木目が見える拭き漆仕上げの食器は日用品です」と教えてくれたのは関美工堂の関昌邦社長。”野に漆”をキーワードとするNODATEシリーズの生みの親だ。

▲関社長
創業1946の年関美工堂は、木製の板に漆塗りと蒔絵を施した表彰用楯を世界ではじめて商品化した企業。3代目となる関社長は、会津漆器の技術をもっとカジュアルに、日常的に取り入れてほしいと漆器ブランドを立ち上げており、そのひとつがNODATEシリーズだ。

▲熱いコーヒーも、手に伝わるのはぬくもりだけ
「漆器をしまい込んでハレの日だけ使うのではなく、普段使いしてほしくてbitowaやurushiol、NODATEというブランドを立ち上げました。
ただ、NODATEシリーズはアウトドアの印象が強いためキャンプでしか使わず、普段はしまっているという人もいるようで。アウトドアでも日常でも使ってほしいですね」(関社長)
HHTでNODATEシリーズの工程をチラリ

旧社屋をリノベーションした「ヒューマンハブ天寧寺倉庫(以下、HHT)」は関美工堂の製品+会津ゆかりのグッズや食品を集めたセレクトショップだけでなく、工房やシェアキッチンも併設し、地域の人とモノを盛り上げる役割を担っている。
じつはNODATEシリーズもこちらで製造しており、タイミングがあえば作業する様子をガラス越しに見学できるのも大きな特徴だ。

▲木をおおまかな形に削った荒形
作業は大きくわけて木地師が「木を削って形を整える」、塗師が「漆を塗る」、蒔絵師が「装飾を施す」の3工程。ベースとなる木は水分を含んでいるので、時間を掛けて乾燥させながら作業を進めるという。

この日は木地師がろくろに荒形をセットし、内側を削っていく様子を見学できた。ジグなんてなく、自作の刃物1本で削っていくのだからスゴイ。

製品ごとに厚み、くびれや丸みのはじまる位置などが指定されていて、それを確認するプレートが用意されている。
内側と外側にプレートを木地に当てて隙間がなければ指示通りできたという証で、できあがった木地にプレートを当てるとピタッとはまる。感覚だけで作っても、まず外すことはないそうだ。

最終的に飲み口を厚さ1mmほどに仕上げる。同じ木製でもククサとは違った口当たりのよさが持ち味だ。

こちらは漆塗りや蒔絵を施す場所。研磨する場所よりも気圧を高くして細かなホコリが入らないようにしているそう。奥に見えるのは真空ろくろ。ハンドルを回せば真空になって器が落ちることなく、どの角度でも固定できてきれいに塗れるというもの。
ちなみにNODATEシリーズは塗りこんだ漆を拭き取って木目が見えるようにする”拭き漆”という塗り方だ。

▲漆を塗ったらロウでつく棒にくっつけて乾燥用ボックスへ
漆を塗ったら湿度70%、冬は25℃程度に保つ乾燥用ボックスに入れて仕上げる。かつては弟子が夜中に起きて、漆が垂れ落ちてムラにならないよう定期的に器の向きを変えていたそうだが、今ではつく棒をセットした台がゆっくり回転。もう就寝時間を削ることはない。

塗りおえたNODATEシリーズは、何度も漆を重ねて磨く塗り漆のようなしっとり感は少ないものの使い込むうちに独特のツヤが出る。それに塗膜としては薄いが、コストを抑えられるので手に取りやすい価格。剥げても修繕しやすいことも日常向きといわれるゆえん。

NODATE Mugは下の方に小さな穴を開け、革紐を通して完成する。さかさまに吊しておけるのでホコリを被らず、水気がたまることもない。
底に穴をあけるなんて!…とも思うが、断面を見ればわかるとおり底は思いのほか厚く水漏れの心配はない。厚みがあるのでひっくり返しにくいことも利点と言える。
なぜ工房をシェアしているのか

この日、作業をしていた若き木地師、岸野和貴さん。
東京出身で石川の学校で技術を学んだものの、それを活かす場がなく昼間は大工、空いた時間にHHTで作業しているそう。
「漆器作りが盛んなころは弟子入りして技術だけでなく伝票の書き方や取引先との付き合い方も学び、一部の道具を分けてもらって独立できていました。
けれどもひとり弟子をとると、その期間は指導などに時間をとられてその工房での生産量が減る。弟子が成長し独立するまでの間は工房の生産量は倍増しますが、そうやって職人を増やしていけるのは市場が右肩上がりのとき。
平成元年をピークにニーズが激減した今では多くの工房が廃業してしまいました。技術は学校で教えてくれますが、定期的な仕事があるかもわからない新人が大型の機械をいきなりそろえるのは現実的ではありません。この状況で職人が増えるわけはなく、数少ない職人に仕事が集中。全国的に職人不足なんです。HHTのシェア工房が若い職人をサポートする場となれば」(関社長)。
登録した職人は工房の機材を自由に使ってよく、関美工堂以外の製品を作ってもいい。一方、関美工堂はNODATEシリーズをはじめとする漆器作りを依頼して生産数を確保できる。独立した職人が増えれば、漆器業界が活気づく。シェア工房を軸に、三方よしを目指す。

シェアキッチンは、地域の農作物生産者や飲食店が加工食品開発を行うのをサポート。漆器だけででなく地域を丸ごと盛り上げようというわけ。
「若い頃は(当時)マクドナルドもスターバックスもないこの町では何もできないと、東京に飛び出しました。父が倒れ、嫌々帰ってきた訳ですが、今はこの町で暮らすのを誇りに思います」(関社長)
剥げたり割れたりしたら再塗装や金継ぎで補修

▲補修することで唯一無二のマグに変身
海外では陶器=China、漆=Japanと呼ばれるほど日本の漆は高品質だが、NODATE Mug誕生から今年で15年。初期モデルのユーザーの中にはトラブルに悩んでいる人もいるだろう。
うっかり落として割れたり漆が剥げたりすると、そこから水分が入り込んで木地に大きなダメージを与えてしまう。早めに適切な補修を行えば100年は使い続けられるので、まずは相談を。

HHTでは関美工堂の漆器だけでなく、陶器やガラス製品の金継ぎも行っている。これも思い出の製品がよみがえるうれしいサービスだ。
HHTでの楽しみ方はイロイロ

▲「NODATE Mug yokoki」(左)と「NODATE Mug」、どちらを選ぶか悩ましい…
NODATE シリーズのマグには、歪みが少ない縦木取りの「NODATE Mug」と、芯も無駄なくとれてユニークな模様ができる「NODATE Mug yokoki」がある。
デザインも「NODATE Mug yokoki」は底が丸く、「NODATE Mug」は浮いて見えるといった違いがある。木目や色味、デザインの違いを見比べながら製品を選べるのはHHTという実店舗ならではのよさ。

ちなみにHTTにはカフェが併設されており、NODATEシリーズの食器で無農薬、化学調味料のない会津地方の食を楽しめる。料理を載せたときの雰囲気、飲み物を入れたときのマグのぬくもりを体感できる。

HHTの2階はコワーキングスペースで、一角にボトルや布製品にプリントができるプリンターを備えた「HHT Print Lab.」があり1点だけプリントするなんてこともOK。NODATE Mugに収納袋はついていないが、手持ちの袋や風呂敷に自分で描いたイラストをプリントして持ち運び用の袋を作るという手もある。

スキーやキャンプ、登山などアウトドアアクティビティの盛んな会津地方に向かうなら、HHTに立ち寄ってみてはいかがだろう。漆器と会津の文化に触れると旅の充実度が増すのだから。
【問】関美工堂 https://sekibikodo.jp