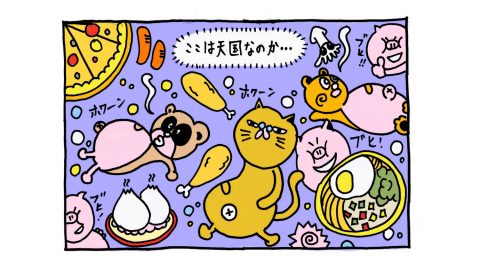現代の冒険は目標への到達より「過程」が重要だ

探検家・関野吉晴さんが、時代に風穴を開けるような「現代の冒険者たち」に会いに行き、徹底的に話を訊き、現代における冒険の存在意義を問い直す──BE-PAL3月号掲載の連載第44回は、サバイバル登山家 服部文祥さん、ノンフィクション作家・探検家 角幡唯介さんとのスペシャル鼎談が掲載されています。
自給自足の山旅を続ける服部さん、冬の北極圏を毎年旅し続けている角幡さんとともに、関野さんが、「従来の目的地の到達のみをゴールとする到達主義的冒険」の対極にある「到達主義でない冒険」を考えます。
関野吉晴/せきの・よしはる
1949年東京都生まれ。探検家、医師、武蔵野美術大学名誉教授(文化人類学)。一橋大学在学中に探検部を創設し、アマゾン川源流などでの長期滞在、「グレートジャーニー」、日本列島にやってきた人びとのルートを辿る「新グレートジャーニー」などの探検を行なう。
服部文祥/はっとり・ぶんしょう
1969年神奈川県生まれ。登山家、作家。山岳雑誌『岳人』編集者。1996年K2登頂。その他、冬の黒部などで複数の初登攀記録を持つ。1999年から、装備と食料を極力持ち込まず身一つで挑む「サバイバル登山」を実践している。近著『今夜も焚き火をみつめながら』(ネイチュアエンタープライズ)ほか著書多数。
角幡唯介/かくはた・ゆうすけ
1976年北海道生まれ。『エベレストは登らない』を本誌連載中のノンフィクション作家、探検家。早稲田大学探検部OB。著書に、『地図なき山:日高山脈49日漂泊行』(新潮社)、開高健ノンフィクション賞受賞作『空白の五マイル』(集英社)、本屋大賞2018年ノンフィクション本大賞、大佛次郎賞受賞作『極夜行』(文藝春秋)など。
到達主義でない冒険はわかりにくい
関野 「目的地の到達のみをゴールとする近代到達主義が冒険をつまらなくしている」というのがわれわれ3人の共通認識です。到達主義でない冒険は、効率は悪いけれど面白い。到達主義は、目的地に向かっているときに、その周りに面白いものがいっぱいあるのに寄り道をしません。
たくさんのものを捨てている。それがもったいない。もっと面白いものがいっぱいあるから、もうちょっと過程を楽しもうよというのが、私が考える到達主義でない冒険です。
服部 効率よく目的地に到達することを求めてきたのが近代の冒険でした。そんな到達主義的な行為によって冒険は発展してきました。それが行き着くところまで行き着いて、僕らみたいのが出てきて、「過程のほうが重要なんだ」とか「自分の力でやるほうがいいんだ」とかいっているわけです。
効率よく目的地に到達することを求めてきた冒険に対して、急にそれをひっくり返して、「そうじゃないよ」みたいな。
角幡 ただ、僕らがいっていること、やっていることが伝わるかというと、難しいとも思うんですよね。過程を重視する方向に進むと、結果が見えにくくなるじゃないですか。やっている本人は充実しているけれど、結果が見えにくくなるから周りにその良さ、すごさが伝わりにくくなる。
だから、メインストリームにはたぶんならないと思うんです。むしろ、今後はさらにスポーツ化に向かっていくのではないでしょうか。記録を競うといったように、数値化されたわかりやすい冒険がメインストリームになるような気がします。
関野 到達主義でない冒険は、達成感が薄いという面もありますよね。到達主義の冒険だと達成感やモチベーションがわかりやすいけど、到達主義でない冒険は、「あそこを目指すぞ!」とか「前に進むぞ!」といったモチベーションがあやふやになってしまう。もっといえば、何かを克服しようといった向上心が鈍るように思います。
角幡 目標が持ちにくいっていうのはありますよね。僕のグリーンランドの「地球最北部“庭“化計画」でも、はっきりした到達目標地点がないから、正直なところマンネリ化しがちです。
「ここに行かなければならない」というものがないため、厳しい自然の中での活動であっても生活に近づいてきてしまっていると感じるときがある。極地全体が生活のフィールドになってしまったら、偉大なるマンネリになってしまう。自分の中でそのときどきのテーマを設けながらやっています。
関野 到達主義でない冒険にもさまざまな罠、弱点がある。我々3人はそれを自覚する必要がありますね。
この続きは、発売中のBE-PAL3月号に掲載されています!
公式YouTubeで対談の一部を配信中!
以下の動画で、誌面に掲載しきれなかったこぼれ話をお楽しみください。