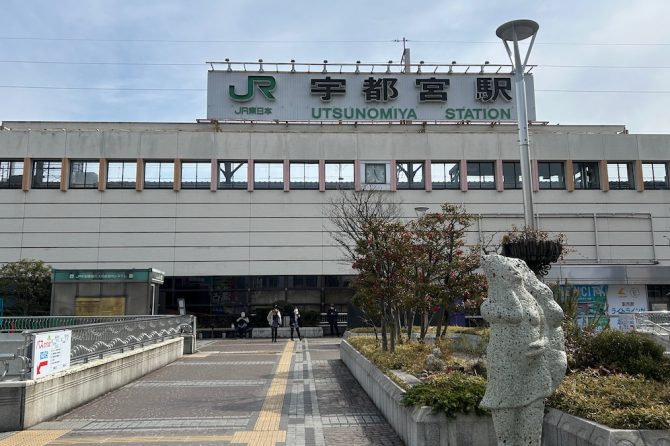始まりは2001年、地元に300年伝わる獅子舞の祭礼だった。21世紀を迎えるにあたって、100年先の赤沼の未来につながるタネをまこうと、地名の赤つながりで赤米づくりに着手。それが味噌になり、餅になり、ビールになって、埼玉県春日部市内の名物になろうとしている。地産地消を地で行く「地ビール」の挑戦の物語。経営する筒野広康さん、隆広さん親子にインタビューした。
赤米を活かす――たどり着いた答えはビールだった
埼玉県春日部市。東京スカイツリーラインせんげん台駅からバスを使って15分ほど。まだ田畑の残る県道沿いに赤沼ロマンブルーイングがある。
ブルワリーから徒歩5分ほどの所に、赤沼香取神社がある。江戸時代から続く獅子舞を地元の人は大切に守ってきた。21世紀を目前にした280年祭のとき、「祭礼を通して100年先につながる事業を考えよう」と「地元の赤沼地域のまちづくりを考える会」が発足した。そのメンバーのひとりが赤沼ロマンブルーイングのブルワーであり代表の筒野広康さんだ。当時46歳。
赤沼の“赤”つながりで赤米を作ろうということになった。筒野さんの本業は自然食の販売。自身でも無農薬野菜に挑戦、肥料や飼料の生産に携わってきた経験が長い。それに赤沼地域には使える田畑は十分にあった。
赤米は昔から生産されてきた米で、今では古代米と呼ばれる。その名の通り籾柄が赤い。日本のお米のルーツをよみがえらせ、次の世代に伝えていこう、そんな趣旨だった。

赤沼で生産されている赤米。
考えるべきは収穫された赤米の使い途だ。2002年、初収穫の当初は知り合いの酒蔵に依頼して、日本酒を造ってもらった。しかし、赤米を原料にした日本酒づくりは、かなり大変なことらしい。
「甑(こしき)などの道具が真っ赤になってしまったそうで、酒蔵から“迷惑な酒”だと言われてしまいました」(筒野広康さん)。日本酒造りは1回で断念した。
どうしたものかと考えあぐねていたある日。ふと、いつも飲んでいる缶ビールを見ると、原料表示が目に入った。そこには麦芽やホップのほか、米、コーン・スターチとある。
「調べてみたら、米を入れるとビールがスッキリすると。それなら赤米でもスッキリして女性にも飲みやすいビールができるのではないか」
春日部市の商工会議所に相談に行ったところ、静岡県・御殿場にあるビール工場を紹介された。OEMのビール生産もしている。筒野さんは赤米を持って、こんなふうにオーダーした。「苦すぎない、ちょっと甘みを感じる、スッキリとしたビールにしてください」
技術も実績もあるビール工場である。数か月後、望み通りのビールに仕上げてくれた。
それを「赤沼ロマンビール」と名づけ、第1回の醸造は、市政50周年に合わせて2004年に発売した。そのビールは2019年まで15年で20回、醸造された。しかし2020年。コロナ禍によって中断に追い込まれた。

2006年に地域の小学生を対象に赤米の田植えや稲刈りの体験学習が始まった。収穫された米は市内の学校給食にも提供されている。
コロナ禍転じて自社ブルワリーの設立に
OEM生産だった「赤沼ロマンビール」は、そのままフェイドアウトしてもおかしくなかった。しかし、すでに地域でその名が知られ、春日部市主催のフードセレクションにも認定されていたビール。なくしてしまうには惜しい。
ビール事業を続けようと、筒野さんは醸造免許を申請した。そして自らは栃木県の栃木マイクロブルワリーで醸造の研修に。右腕になったのは息子の筒野隆広さんだ。本人がクラフトビール好きであることに加え、長年にわたり春日部の活性化に取り組んできた父を応援するため、また少しでも地元の活性化につながればと思い、ブルワリーづくりに参加した。
ブルワリーは今まで味噌造りをしていた工房をリノベーションすることにした。醸造設備を一から調べ、タンクを中国から直取引で輸入した。「説明書が付いてないんですよね」(隆広さん)。それでも電気系統など安全面に関わる部分を除いて自力で組み上げた。2023年4月、醸造免許を取得。赤沼ロマンブルーイングが誕生した。

タップルームが併設された赤沼ロマンブルーイング。車で訪れ、グラウラーでお持ち帰りする常連さんが多い。

赤沼ロマンブルーイングを経営する筒野隆広さん(左)と広康さん親子。
醸造所のすぐ隣に麹室
赤沼ロマンブルーイングの強みは、自前で米麹を作れることだ。自然食に造詣の深い広康さんは赤米で米麹をつくり、それで味噌を作って販売していた。甘酒や塩麹など、健康食品にも米麹はよく使われる。
米麹は米に菌を植え付けて発酵させた発酵食品。米を蒸して、種こうじ(麹菌)をつけて発酵させると米のデンプン質は糖分に、タンパク質はアミノ酸に分解される。製麹には職人技を要する。
先に述べたように、日本では麦芽の仕込み工程で米を加えるビールは珍しくない。しかし赤米の麹を加えるビールは赤沼ロマンブルーイングならではだ。赤沼ロマンブルーイングは醸造所のすぐ隣に米麹を作る麹室がある。マイクロブルワリーの数は現在、国内800以上あると言われるが、醸造室の隣に麹室があるブルワリーがほかにあるだろうか?
今年の「ジャパン・グレートビア・アワーズ2025」で赤沼ロマンブルーイングは、2つのビールで銀賞を受賞した。「ひとまず、クラフトビール界の認定試験に通った感じ」と、広康さんは認識している。

醸造施設にある麹室。自前の麹室がある希有なブルワリー。

左から「きんロマン」(IPA)、「あかロマン」(ペールエール)、「くろロマン」(ポーター)、「しろロマン」(ウィートエール)。
一級品の茶葉を使った「お茶ビール」で新カテゴリーを
2024年、隆広さんが茶葉を使った「お茶ロマン」を造り始めた。茶葉を使うクラフトビールは全国でいくつか見られる。製茶工程で出る葉のカスを利活用したフードロス削減にもつながるビールだ。しかし、「お茶ロマン」はそれらとはコンセプトが異なる。
茶葉はお隣の越谷市の茶屋からわざわざ仕入れる。しかも、「ふだん自分が飲んでいるお茶の数倍する上質なお茶です」(隆広さん)。
「赤沼地域にも昔はお茶畑がありました。伝統的なお茶文化と、赤米を使ったビールを融合させることで新しい飲み物体験を提供したい。お茶ビールというユニークなカテゴリーをつくって、大手ビールメーカーとは異なる市場で勝負したいと考えています」
これまで筆者が飲んだことのある茶葉を使ったクラフトビールは、お茶がほのかに香るビールだった。が、「お茶ロマン 緑茶ビア」は、茶の深みやシブみがはっきり立つ。まさに急須から注がれたようなビールだった。
ビールスタイルでいうと何になるのか尋ねたが、「ペールエールかな?」(隆広さん)と明確ではない。現在、「緑茶ビール」というスタイルはあるが、それとも異なるようで、もしかしたら新たなビールスタイルになるかも? である。
それにしても、なぜ一級品を使うのか? 赤沼ロマンブルーイングには、原料にB級品の農産品を使うという発想はない。赤米もA級品を使っている。
そこには長年、自然食や有機栽培に携わってきた広康さんのこだわりがある。「いいビールを造るならいい原料が必要です。小さいところほどいい原料を使わないといけません」

お茶ロマンブランドの「緑茶ビア」と「アールグレイビア」。ほかに「ほうじ茶ビア」「ウーロンビア」もある。
麦藁帽子のように100年続く事業を育てる
今も赤米は「赤沼地域のまちづくりを考える会」の農家と有志たちが栽培している。2反の田んぼで、収量は12俵。今はささやかな量だが丹精込めて作った赤米でビールを醸造し、地元の店で売る。あるいはタップルームで飲んでもらう。買っていってもらう。まさに地ビールである。
では、当初の目的である赤沼地域のまちづくりに、「赤沼ロマンビール」はどのように寄与しているのだろうか。
埼玉県の春日部市の名産は?と聞かれて、サッと出てくる人は少ないと思う。「特産品がないのが、ずっと地域の課題でした」と筒野さん親子は言う。
赤米は、ビール以外にも活用されている。生地に赤米粉を使った「赤米ドーナツ」や「赤米餃子」は、春日部市のフードセレクションに認定されている。
地域コミュニティへの波及効果も見られる。2024年度からは赤沼農水里環理組合のメンバーが、赤米の農作業に協力してくれることになった。また、近くの養老施設がスペースを一部、開放してくれることになった。今後はそこで地域の人たちが集まって農作物を仕分けたり、養老施設のお手伝いをしたりといった活動ができそうだ。
「私たちが目標にしていた、次の100年につながる事業づくりのタネ蒔きはできたかなと思います。ここまで続けられたのは、やはりビールのおかげかなと思うんですよ。農作業をするにも祭りの準備をするにも、ビールがあると、なんだかエンジンがかかる。ビールがあると何かと広がる。まちづくり継続のためにも、ビール事業をしっかりやっていきたいですね」
地域の活性化を目的に始まった赤米づくりがビールになり、そのビールが巡ってまちづくりのエンジンになっている。
最後に、赤沼地区に100年伝わる技術がひとつある。麦藁(わら)帽子だ。今も90歳代の職人を中心にがんばっている。なぜ麦藁帽子なのかというと、明治時代にここで麦が作られていたからだ。ビール醸造所があった時期もある。大麦はビールになり、麦藁は帽子になった。
広康さんは大麦も復活させたいと考えている。地元産の大麦を麦芽に、赤米の米麹を副原料にしたビールを造り、残った麦藁で帽子を作る。ビールをきっかけに、この先100年続くものが生まれるかもしれない。そんな夢を託して、筒野さん親子はビールに「赤沼ロマン」と名づけた。
●赤沼ロマンブルーイング 埼玉県春日部市赤沼704-2
https://akanumaroman.com