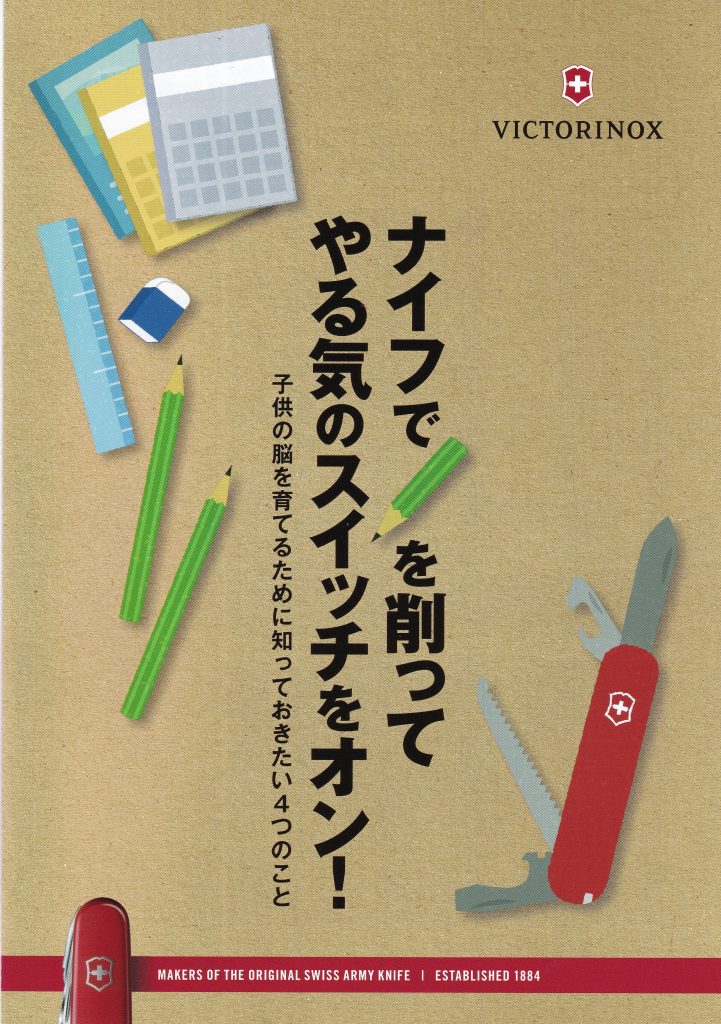何か事件が起きるたびに凶器としてやり玉に挙がり、子供たちから遠ざけられるナイフ。でも、刃物ってそんなに悪者なの? 社会に一石を投じる、ある動きを岐阜県に追った。
ナイフを使う子供は遊びの発想の幅が広い!
非常事態に直面したとき、刃物と火があればなんとか命を守ることができる。これは、日ごろからアウトドアを楽しんでいる多くの人たちの感覚だろう。
だが世間一般となると意識はだいぶ変わる。刃物と火は、もはや社会からは縁遠い存在だ。たとえば魚。今はカット状態でパッケージされているのが普通で、1尾売りされているシーンは減った。電子レンジで温めればすぐに食べられる加工食品も増え、包丁とまな板の出番は確実に減っている。オール電化の家庭では、ガスの炎のゆらぎさえ見ることがない。
農業の世界では、果物の消費が減って困っているという。さまざまな理由があるが「皮をむいて食べるのが面倒」と考える人が増えていることも原因だという。つまり刃物を使いたくない(使えない)日本人が増えているということだ。
「暮らしの中から刃物や火の出番が減っていくのは仕方がないことかもしれませんが、だからこそカバーをする場が社会には必要です。ナイフは子供の成長にとって最高の道具であり、欠かせない存在です。油断すれば指を切って血も出ますが、トライ&エラーを繰り返していくことで安全な使い方が身につき、自ら考え自ら動く積極性が生まれます。子供たちにナイフを使わせると、遊びの発想が確実に広がります。自己肯定感、つまり自信もうんと高まります」
こう語るのは、森林管理や木材のスペシャリストを養成する岐阜県立森林文化アカデミーの萩原・ナバ・裕作さん(47歳)だ。環境教育とインタープリテーションが専門の萩原さんは、岐阜県美濃市にある学内に森のようちえんとプレーパークを開き、地域や保護者とともに自然を核にした新しい教育の形を研究している。
この実践教育の中で数年前から進めている取り組みが、子供たちにもっとナイフを使わせようという『morinocoナイフ』プロジェクトだ。「きっかけは森林文化アカデミーが隣の関市の子供キャンプを引き受けたことでした。関といえば昔からナイフの町として知られています。だったらキャンプでは地元のナイフを使おう。ところが関には子供用のナイフを作っている業者がなかったんですよ。仕方がないので他の産地から買った子供用ナイフを使いました」
そのキャンプが縁で、数年後、関市から森のようちえんについて教えてほしいという打診があった。「森のようちえんとは子供が自然の中で主体的に活動する場で、たとえば世間から危ないと思われている刃物や火も、成長に不可欠と考えるので、幼児のうちから使わせています、と説明したのです。僕はふと以前のことを思いだし、尋ねてみたんです。なぜ関市は刃物が地場産業なのに子供用ナイフがないのですかと。そしたら当時の課長がハッという顔をされ、すぐに刃物組合に連絡をとったのです」
関市は2005年に旧武儀(むぎ)郡の洞戸(ほらど)村、板取(いたどり)村、武芸川(むげがわ)町、武儀町、上之保(かみのほ)村と合併した。山間部の町村が関市に編入されたことで、主要な産業に刃物と並んで林業が加わることになった。
萩原さんの何げないひと言が、地場産業を統合する新しいシンボルとして、木のハンドルの教育用ナイフを作ろうという着想につながったのだ。関市産業経済部の吉田浩之さん(45歳)はいう。
「林業の課題のひとつに、林地残材、つまり建築材としては価値のない枝や梢部分の有効活用があります。県内でもいろんな地域で研究や実践がされていて、バイオマスエネルギーなどの利用例がありますが、関市らしさという視点を取り入れるなら、古くからの地場産業である刃物との融合だろうと。ナイフのハンドル材に適した木は限られているとは聞いていましたが、ヒノキの林地残材を使うという新しさに賭けてみようという結論になりました」
こんな木はナイフのハンドルにならない
木のハンドルはすべりにくく、ぬくもりがある。ヒノキは柔かく削りやすい材質なので、自分の手に合わせてカスタマイズもできそうだ。少なくとも、萩原さんと市役所サイドの段階では理想的なアイデアだった。
「たしかに発想はいいなと私も思いました。ところが、木柄(もくえ)屋さんに相談に行ったら、こんなものはハンドルにならんよといわれまして。そもそも、ナイフのハンドル材に求められてきた木の性質は、まず硬さ。次が素直さです。密度が高くて割れにくく、安定性もいい木を使うのが常識。ヒノキの枝は節があるし、横に伸びていたので重力に対する反発力も抱えています。そこをなんとかとお願いして作ってもらってはみたんですが、最初は不具合の連続でした」
こう語るのは、刃物組合からプロジェクトへの協力を要請されたナイフメーカー、石川刃物製作所の石川修さん(45歳)だ。
萩原さんからの要望は、子供が気軽に使えるよう折りたたみ式でポケットに入る大きさであること。構造をなるべくシンプルにし、価格もなるべく抑える。しかし、子供用だからといって鋼材の質は妥協しない。そしてヒノキ材の手触りを重視し、塗装はしないというものだ。完成したのが、肥
後守(ひごのかみ)のように親指でブレード後端の突起を押さえながら使うナイフだ。刃は木のハンドルに切り込んだ溝の中に収納する。萩原さんはいう。
「一番の課題はやはりハンドルで、アドバイザーとして友人の木工家にも加わってもらうことにしました。子供たちが握りやすい形や大きさも含め、何度も加工方法を変え安定性の向上を模索しました。800人以上の子供たち、親、そして教育者の声をもとに改良を続け、おかげで昨年からようやくお披露目ができるようになりました」
関市の刃物まつりで開いたmorinocoナイフによる木工ワークショップには、親子約200人が参加。大人気のうちに終了した。萩原さんは、参加した親子や見学の若い女性たちの反応から、刃物に対する潜在的な関心の高さを感じたという。
「子供たちも女子も、ナイフを使って遊びたいんですよ。それは道具を使って生きてきた動物である人間にとって、極めて健全な欲求だと思います」
ナイフには、たしかに危険性もある。使っているときは絶えず緊張感にさらされ、油断はすぐケガに結びつく。だが、ときどき痛い経験もすればこそ、刃物を使う責任を自覚するようになる。
危ないという理由だけで予防的に取り上げ、子供たちから刃物を遠ざけることは、社会の選択としてはあまりにも未熟ではないかと、萩原さんは訴える。
「いま子供たちに伝えるべきことは、ナイフがあればたいていのものは作れちゃうんだよということだと思うんです。少し時間がかかるけど、買わなくたって自分で解決できる。そういう当たり前の感覚や自信を、もう一度、社会や家庭に取り戻したいんですよ」
このまま何もしなければ磨いてきた技術も消える
子供たちの刃物離れは、業界としても深刻な問題だ。近年、日本の包丁の性能は海外で評価が高まっており、外国人観光客の土産品としても人気がある。刃物業界全体としてはよい波に乗っている最中といえるが、ことアウトドア用ナイフという部門に関していえば、逆風が吹き続けている。
先の尖ったナイフはいまだ凶器の代名詞だ。アウトドア用ナイフを作ってきた会社の中には、製造の軸足を包丁に移したところも少なくない。石川さんはいう。「僕はこの活動に期待しています。市場を再開拓するというか、こういう機運をみんなで高めていかないと、ナイフの存在意義も、自分たちが磨いてきた技術も忘れられてしまいますから」
morinocoナイフの最終目標は、じつは大人を巻き込むことだ。社会が時間や消費の価値を考え直さない限り、真の教育にならない。子供と一緒にナイフを使い、夢中になれる時間を作る。消費から創造へのシフト。それが真のゆとり社会の姿かもしれない。
ナイフななぜ悪者になったのか?
子供たちに刃物を使わせないようにしようという社会的な機運が巻き起こったのは、’60年に起きた浅沼稲次郎日本社会党委員長の刺殺事件がきっかけだ。学生服姿の右翼の少年が壇上で演説していた浅沼委員長を短刀で襲撃。衝撃的な瞬間の写真が新聞に掲載された。当時は青少年による犯罪が多く、凶器にはしばしば登山ナイフや包丁が使われた。
だが世論は、こうした問題が起きる背景を格差や教育の問題として検証することをせず、警視庁が提唱した、青少年に刃物を売らない、持たせないという運動に乗っていったのである。学校では子供たちがナイフを持ってこないよう鉛筆削り器を使うことが推奨された。機を一にするように子供たちを取り巻く環境も大きく変わった。テレビやゲームの普及で外遊びをしなくなったうえに、暮らしが急速に便利になり、薪割りや料理といった刃物を使う手伝いをする必要もなくなった。その後も刃物の規制は進む。ハイジャック事件が起きるたびに荷物検査が厳重になり、出張などに便利なことから愛用者の多かった小さなツールナイフまでもが持ち込み規制の対象に優れた道具には二面性があるものだが、刃物の場合、なぜか罪の部分ばかりがクローズアップされやすい。浅沼事件の残像が消える日はいつだろう?
子供たちに刃物体験が必要な理由…ナイフを使うと脳が活性化!
刃物を使うとき、人は手指と脳の間でさまざまな情報のやりとりをする。このイメージで削れ。指を切るな。作業の質を上げろ。効率を考えろ。周囲にも気を配れ…。それらのレスポンスはつねに瞬間的、かつ複合的で、やりとりされる情報量は膨大なものになる。こうした作業の繰り返しには、人間の脳を活性化する効果があるのではないかという指摘は昔からあった。この仮説を具体的に検証したのが、ツールナイフで知られるビクトリノックス・ジャパン株式会社と、科学技術による教育開発を行なっている株式会社リバネスが、脳活性の研究で知られる篠原菊紀(しのはら・きくのり)さんの協力で2016年に行なった実験だ。
小学生を対象に、ナイフで鉛筆を削ったときと電動鉛筆削り機で削ったときの脳活動を比較。ナイフで鉛筆を削ると、ものを考えたり判断する前頭前野の活動が盛んになることが確かめられた。つまりやる気のスイッチが入るのだという。さらにナイフを使う前と使った直後のテストでは、使用直後のほうが注意力を測る課題テストの成績が高まることが明らかになった。これは他人への配慮、つまりやさしさにもつながる能力だそうだ。
ナイフの使い方を教える指導者を増やすことも急務
遊びや生活の中で、刃物を使う機会がないまま大人になってしまったという人は意外に多い。親がアウトドアを楽しんでいる場合は子供もナイフを使えるケースは多いが、このままだと〝指先格差〟は拡大する一方だ。いま、刃物業界や教育関係者の一部で議論されつつあるのが、刃物の使い方を教える指導者の育成と、共通の指導マニュアルの作成だ。
ナイフ使いの名人である必要はないが、刃物の基本的な使い方と楽しさ、安全管理をバランスよく教えられる人材は教育やアウトドア関係者の中に一定数は必要だ。そうでないと刃物に対する世間の偏見は払拭できない。岐阜県立森林文化アカデミーの萩原・ナバ・裕作さんは、急がなければならないのは、子供たちに最も近い若い保育士や教師、キャンプリーダーへの技術伝授だという。
石川刃物製作所の石川修さんは、実現には刃物産地の連携がカギになると語る。これまでも一部で交流はあったが、教育のような視点で話し合いをしたことがない。産業の将来にも直結していることなので、シンポジウムのようなものをきっかけに多くの人たちと交流を深めれば、打開策は必ず見つかると考えている。
結果として日本の刃物分化が多彩になり、ナイフを使うことが教養のひとつに認められる時代が来れば、それこそが成熟社会の証だろう。
※取材・撮影/鹿熊 勤 参考/『刃物と日本人』日本エコツーリズムセンター編(山と溪谷社刊)
※この記事はビーパル11月号に掲載された「ルーラルで行こう!vol.42」を再編掲載しています。
「ルーラルで行こう!」は、12月発売の1月号からリニューアル!「自然は資源、人は価値。幸せの風は地方から。 田舎賢人!」として装いも新たに登場します!お楽しみに。