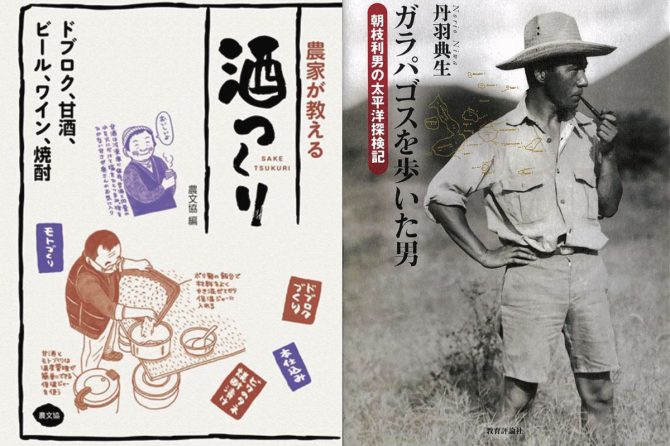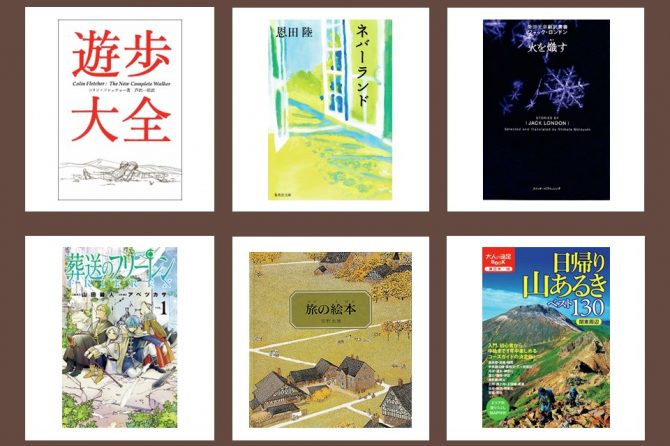中国四川省にあるチベット仏教の僧院、ラルンガル・ゴンパ ©Uruma Takezawa
「この本を書くのは、大変でした。本当に、すごく苦労して。初めから明確なゴールは見えてなかったし、自分で納得できるかどうかもわからなかった。どこに辿り着くかわからないまま、書きながらずっと考え続けて、旅の最後まで書いた時に、初めて浮かんできた言葉があって……。それは、意外にシンプルな言葉でした」
インドのスピティやザンスカール、ネパールのムスタン、中国の青海省と四川省など、世界各地のチベット文化圏を足かけ3年にわたって旅した、写真家の竹沢うるまさん。その旅の中で起こった出来事や出会った人々、そして竹沢さん自身の思索の変遷が綴られた紀行文『ルンタ』が発売されました。同じ旅をテーマにした写真集『Kor La』と対を成す存在であるこの本は、かつて竹沢さんが3年弱の歳月をかけて世界103カ国を旅した後に発表した写真集『Walkabout』と紀行文『The Songlines』の続編にもあたる存在です。

インド北部スピティ地方の僧院、キー・ゴンパ ©Uruma Takezawa
忘れられない出来事が、次の旅に踏み出すきっかけになった
竹沢さんをチベット文化圏を巡る旅へと向かわせたのは、『Walkabout』と『The Songlines』で描かれた3年近くに及んだ旅の終盤に、中国の四川省で遭遇した出来事でした。バスに同乗していたパンツォという名のチベット人の青年が、検問所で公安の係官たちに何の理由もなく車外に引きずり出され、無抵抗のまま、殴る蹴るの暴行を受けたのです。
「あれは、ものすごく衝撃的な出来事でした。あらゆる方向から心を揺さぶられて、それが長い旅を終える直接的なきっかけにもなって。『Walkabout』と『The Songlines』を作った時、あの出来事は、もちろん重要ではありましたけど、3年弱の旅の中での一出来事という位置づけにしていました。でも、よくよく考えてみると、これまでの人生の中で、あれほど暴力的な出来事を経験したことはなかったし、別れ際にパンツォが見せてくれた表情ほど、人の優しさに触れた経験もなかった。だから、旅を終えた後も、ふとした折に記憶の断片がフラッシュバックするような感じで、よく思い出していたんです。あの時、自分はパンツォに、何を返せたのかな。彼が公安に殴られていた時に、何かすべきだったんじゃないか。その後、彼がこっちを気遣ってくれた時に、何か返すべきだったんじゃないか。その二つが抜け落ちていた気がして、ずっと心残りだったんです」
その出来事の意味を、自身の中であらためて見つめるため、竹沢さんはチベット文化圏を巡る旅に出ることを決意します。
「チベット文化圏のどこをどう回るかは、行ったことのない場所、経験したことのないもの、という基準で選んでいきました。スピティ、ムスタン、冬のザンスカール、青海省……。でも最後には必ず、あの出来事が起こった、四川省の検問所があった場所に行こうと、決めていました。最後にあそこに行くまでに、旅をしながら考える時間がほしかったんだと思います。すぐにあの場所に行っても、何も見えないだろうなあ、という感覚はあったので。過去をふりかえりながら旅に出るのは、初めてでした。新しい場所に向かいたいけれど、道が見えない。見えないけれど、でも、行かないとなあ、と」

インド北部ラダック地方の少数民族ドクパの女性 ©Uruma Takezawa
祈りは、自分が確かに存在していることのステートメント
チベット文化圏を巡る竹沢さんの新たな旅は、予期していた以上に過酷なものとなりました。標高3000メートルを超える高地で、高山病に苦しみながら、村から村へと徒歩で旅することもあれば、マイナス20℃を下回る寒さで凍結した川の上を、死の恐怖と戦いながら歩き続けることもありました。そんな過酷な旅の中で、竹沢さんが出会ったのは、大地に根ざした素朴な暮らしを営みながら、自然や仏への祈りを胸に抱いて生きている、心穏やかな人々でした。
「祈りというものは、いったい何なのか。旅の間、ずっと考え続けていました。この地球上で、祈っているのは人間だけなんですよ。主体となる人間がいて初めて、対象となる神や大地や自然に対して、祈りが生まれる。主体として心がある人間が存在していて、その心の動きが穏やかであれば、本当の意味での祈りにつながっていく。祈りの正体は、自分自身が確かにここに存在している、というステートメントだと考えています。その祈りを常に感じることができていれば、心の豊かさにつながるんじゃないかと思うんです」
足かけ3年に及ぶチベット文化圏を巡る旅を終えた後、旅の経験と自身の思索の変遷を言語化して『ルンタ』という本に結実させるのは、想像以上に大変な作業だったと竹沢さんはふりかえります。
『この本の原稿は、8回くらい書き直したんです。ずっと書きながら悩んでいて、編集者さんからも助言してもらいながら、あらためて考え直して。それで気付いたのは、竹沢うるまの書く旅行記の特徴は、自分の内面と向き合うということ。旅っていいよね、とか、世界は広いよね、とかではなく、自分の内面と旅との間の橋渡しというかバランスの取り方を語るのが、特徴なのかな、と。自分自身の物語と旅との融合という本来のスタイルが明確になってからは、書きやすくなって、それからはバーッと書き進めていきました」

インド北部スピティ地方の僧院で制作され、法要後に崩される砂曼陀羅 ©Uruma Takezawa
書き終えた時に初めて見えた、「ありがとう」という言葉
『ルンタ』の原稿に取り組みながら、竹沢さんが思い出していたのは、旅の途中で見る機会のあった、チベット仏教の僧侶たちが色付きの砂で描いていた砂曼陀羅だったと言います。本を書く作業もまた、砂粒を置くように一字一字を置いていって、図柄を作っていくのに近い感覚だったそうです。
「砂曼荼羅は完成した時に初めて、その図柄が見えてきますよね。自分が原稿を最後まで書き上げた時、初めて見えてきたのは……“ありがとう”という言葉でした。長い旅を終えるきっかけを与えてくれたことへの感謝。そこからさらに新しい旅にもう一歩進むきっかけを与えてくれたことへの感謝。“ありがとう”という言葉は、相手を全面的に信頼することで、初めて出てくる言葉だと思います。それが、あの時、自分がパンツォに伝えたかった言葉であり、本を書き終えた今の自分の言葉でもある。あの当時は、“ありがとう”という感謝の言葉までは、明確に浮かんでいなかった。子供だったからです。自分中心でしか、世界を見ていなかった。“個”でしかなかった自分が、“全体の中の個”であることに気付いた。“全体の中の個”として存在させてもらっていることに対する感謝。あの出来事から長い時間を経て、ようやく自分の心を開いて、自分がこの世界自体に組み込まれていることを、違和感なく受け入れることができた。だから、“ありがとう”という言葉が素直に出てきたのかな、と思います」
今回の『ルンタ』が、過去の竹沢さんの著作で用いられていた“僕”ではなく、“私”という一人称で書かれているのも、そうした心境の変化を反映したからだと竹沢さんは言います。
「今回は“僕”じゃないな、“私”だな、と思いました。“僕”だと甘えがあるというか。心が開かれて、“全体の中の個”であることに気付いて、感謝の気持を持った時、“ありがとう”という言葉を言えるのは、“僕”ではなくて“私”かな、と。『The Songlines』の“僕”から『ルンタ』の“私”への変化は、大きな違いがあると思います。文章だけでなく、たぶん写真も、捉え方が“僕”から“私”に変わっているはずなんです。これまでの延長線上にあるだけの写真ではなくなっています。ようやく独り立ちしたというか、すべてを受け入れて、じゃあ、歩いて行きますか、というところにまで来れたのかな、と思います」
竹沢うるま Uruma Takezawa
1977年生まれ。ダイビング雑誌のスタッフフォトグラファーを経て2004年より写真家としての活動を開始。主なテーマは「大地」。そこには大地の一部として存在する「人間」も含まれる。2010年〜2012年にかけて、1021日103カ国を巡る旅を敢行し、写真集『Walkabout』と対になる旅行記『The Songlines』を発表。2014年第三回日経ナショナルジオグラフィック写真賞受賞。その後も、チベット文化圏を捉えた写真集『Kor La』(小学館)と旅行記『ルンタ』(小学館)など、写真と文章で自身の旅を表現している。最新作は写真集『Boundary | 境界』(青幻舎)。「うるま」とは沖縄の言葉でサンゴの島を意味し、写真を始めたきっかけが沖縄の海との出会いだったことに由来する。

『ルンタ』
竹沢うるま 著
小学館 本体2500円+税
写真集『Kor La』と対を成す、足かけ3年、チベット仏教圏を巡った祈りの旅の記録。

『Boundary | 境界』
竹沢うるま 著
青幻舎 本体6000円+税
写真家竹沢うるま、約4年半ぶりの新作写真集。アイスランドの大地の風景を通じて、人と人とを分かつ“境界”の意味を問う。

竹沢うるま 写真展「Boundary | 境界」
アイスランドで撮影された圧倒的な「自然の大地」と日本の国東半島で撮影された「人間の大地」、約25点を展示。「境界とは何なのか?」を見る者に問いかける。
キヤノンギャラリー銀座:2021年4月20日(火)〜5月8日(土)(日・月・祝 休館)
キヤノンギャラリー大阪:2021年6月8日(火)〜6月19日(土)(日・月・祝 休館)

竹沢うるま×山本高樹「空と山々が出会う地で、祈りの在処を探して」
『ルンタ』『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』W刊行記念トークイベント
2021年4月17日(土)19:00〜 本屋B&B
詳細はこちら→ https://bb210417c.peatix.com