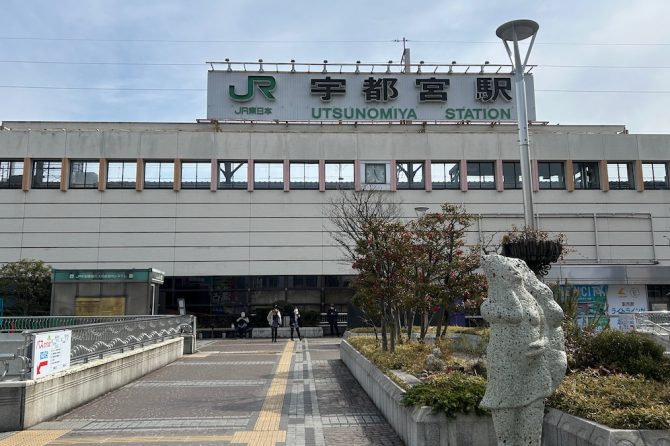モアン山で絶景を堪能
中標津町で酪農を営む佐伯雅視さんを訪ねて、厳冬の北海道を旅した。
佐伯さんは全長71kmのロングトレイル、北根室ランチウェイの創始者だ。ランチウェイの名が示すとおり、ランチ(牧場)をつないで中標津空港から摩周湖を経てJR釧網本線の美留和駅まで歩く1本の道を、佐伯さんは私費を投じて整備した。地平線が望める開陽台や無料露天風呂の養老牛温泉、西別岳など、見所も多く、雄大な北海道の自然を堪能できるロングトレイルとして多くのハイカーに愛されたが、2020年の秋に北根室ランチウェイは全面閉鎖された。

スコットランドのウエストハイランドウェイを参考にした北根室ランチウェイ、牧場を通る箇所もあるため、牛は通れず人間だけが乗り越えられるマンパスが設置されている。
どのような経緯があったのか、本人の口から直接聞きたくて佐伯さんを訪ねたわけだが、その内容に関しては発売されたBE-PAL4月号の連載『シェルパ斉藤の旅の自由型』に記したので、そちらを読んでもらいたい。
僕は2015年の夏に北根室ランチウェイを歩いたが、今回はそのとき歩けなかったモアン山や冬ならではの絶景も訪ねて回った。

標高357mのモアン山。外国の商売人に使われないように佐伯さんはMOANを商標登録している。

モアン山の頂上では360度の絶景が楽しめる。西にそびえる山は北根室ランチウェイのコースでもあった西別岳と摩周岳。

モアン山でスキーを楽しむ女性と出会った。冬でも気軽に登れる山として人気が高い。

レンタカーを使って開陽台にも出かけた。かつてライダーの聖地と呼ばれた場所で、何度か訪れているが、冬は初めて。空気が澄んでいるからか、夏の風景よりも美しく見える。
架線のない釧網本線で美しい景色を堪能
後半は鉄道の旅も楽しんだ。
JR北海道はSL冬の湿原号を運行しており、1月から3月にかけて週末を中心に往復1便のSLが釧網本線の釧路駅と標茶駅の約48kmの区間を走行する。往路は釧路駅を11時5分に発車して標茶駅に12時35分に到着、復路は標茶駅を14時に発車して15時42分に釧路駅へ到着する運行スケジュールになっている。
レンタカーで巡っていた僕は、最初に標茶駅へ行って駅前の駐車場にレンタカーをとめ、普通列車で釧路駅に出かけて11時5分発のSL冬の湿原号に乗車して標茶駅に戻る計画を立てた。

冬の釧路川でカヌーをしている人々を列車から見かけた。寒いけど、絶景なんだろうな。
切符の入手がむずかしいSL冬の湿原号と違って、普通列車は空席が目立つ。列車の先頭部に移動して、運転席のすぐ脇で車窓の風景を楽しんだ。非電化の釧網(せんもう)本線は架線がないから視界が遮られず、風景がすっきりと見える。広々とした釧路湿原を眺めて写真を撮っていたら、線路にエゾシカ数頭が現れた。
運転手さんが汽笛を鳴らすも、すぐには移動しない。線路脇にいた1頭は汽笛を鳴らしたら線路内に出てきてしまった。

列車の前に飛び出てきたエゾシカ。いきなり飛び出すから列車は徐行運転しなくてはならない。
「カンが鈍い奴だなあ」と声に出したら、運転手さんが笑って「この区間はエゾシカが多いんですよ」と答えた。そういえば10年近く前に駅名のしりとりで冬の北海道を鉄道で巡る旅をした経験があるが、そのときは乗車した列車がエゾシカをはねてしまい、エゾシカの処理に時間がかかって大幅に列車が遅れたことを思い出した。
SL冬の湿原号に乗車!
釧路駅はSL冬の湿原号に乗る観光客たちでにぎわっていた。
アナウンスが流れ、SL冬の湿原号が煙をはいてゆっくりとホームに入線してくると人々はカメラやスマホを構えてホームに殺到した。

モクモクと煙をはいて入線したSL冬の湿原号。存在感は半端ない。雪景色がよく似合う。

スマホで撮影する人々でホームは混雑した。中国人の姿も多かった。
釧路は最高気温がほぼ氷点下だった。空気が冷え切っているから、蒸気の白さが際立つ。鉄の塊である機械なんだけど、あちこちから蒸気が漏れて存在感が際立つ姿は、クジラのような巨大な生き物を思わせる。それほど鉄道が好きではない僕もその迫力に魅せられ「撮り鉄」となって何枚も写真を撮った。
ちなみに北海道の人々は列車を「汽車」と呼んでいる。これこそ本物の汽車だと納得した。

呼吸しているように思えたSLの蒸気。たくましさを感じた。

カワサキのオートバイのオーナーでもある僕は、川崎の文字に親近感をおぼえた。
人々の心を揺さぶるSLの魅力
昨年はSLの機械にトラブルが起きて、SL単体で運行することができず、ディーゼル機関車に押してもらうスタイルで運行したそうだが、今年はSLのみの運行である。
頼もしきそのSLは1940年に製造されたC11形機関車。製造から83年も経つ年代物だが、連結されている客車はレトロな雰囲気の新型車両になっている。乗客は親子連れもいれば、若者も年配の方もいて、SLが幅広い年齢層に愛されていることを実感した。

SLの操縦室。電子部品がなく、無骨な鉄のバルブやレバーを人の手で動かして運転する。かっこいい!

2・3・4号車はダルマストーブが設置されていて、スルメを焼くこともできる。新型車両はどれも快適で、SLらしさに欠けるマイナス面も感じる。
定刻の11時5分にSL冬の湿原号は発車。汽笛が鳴り響いた瞬間、胸が震える感動をおぼえた。1961年生まれの僕は幼少の頃に観光列車ではなく、普通列車としてのSLに乗車した記憶が残っているが、この汽笛は聞き覚えのない人々の心も揺さぶる特別な音だと思う。
SLならではのスローな旅に心がなごむ
釧路駅を定刻通りに発車したSL冬の湿原号だが、ほんの3km先の東釧路駅でトラブルが発生した。レールに積もった雪がSLのフロントに氷となって集積されて車輪が動かなくなったのである。馬力のあるディーゼル機関車だと氷雪を押しつぶして進んでいけるが、非力なSLだとそうはいかない。数m後退して勢いをつけて発進すれば問題ないと乗務員さんが教えてくれたが、後退するには司令室に連絡をとって許可を得なくてはならないとのことだ。
その許可に時間がかかったため、定刻よりも20分程度遅れて東釧路駅を発車したが、顔をしかめる乗客は誰ひとりいない。スローな速度が魅力のSLだから多少の遅延なんて気にならないし、予期せぬトラブルもSLの旅ならではの味に感じられる。
沿線にはSL目当てのたくさんの人々がいて、多くの人が僕ら乗客に手を振ってくれる。それに応じて手を振ると、彼らは笑顔で手を振り返してくれる。
心がほっこりとする冬の旅となった。

標茶駅に到着後、駅前に駐車しておいたレンタカーで復路のSL冬の湿原号を追っかけた。復路は機関車が逆向きになるのが残念。

SL冬の湿原号を追っかけて立ち寄った茅沼駅でタンチョウヅルに遭遇した。かつての駅長が餌場を設置して給餌を始めたのがきっかけでタンチョウヅルが寄りつく駅になったとのこと。最初に見たときは置き物かと思った。