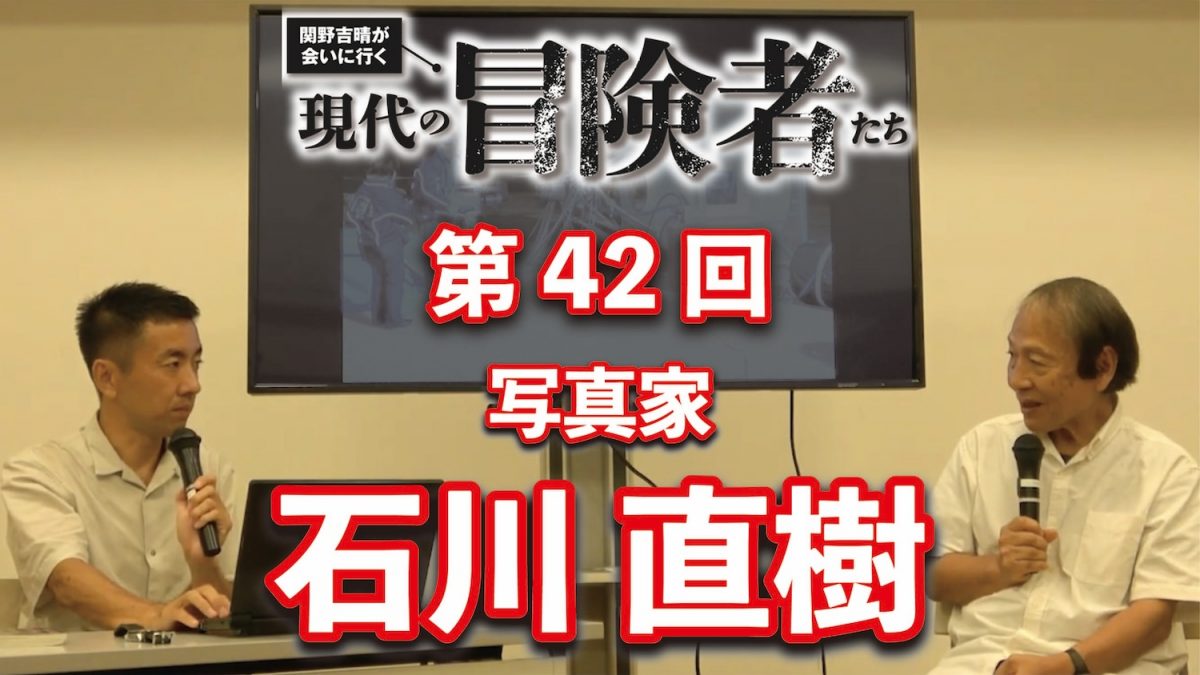探検家・関野吉晴さんが、時代に風穴を開けるような「現代の冒険者たち」に会いに行き、徹底的に話を訊き、現代における冒険の存在意義を問い直す──BE-PAL1月号掲載の連載第42回は、写真家 石川直樹さんです。
ヒマラヤの8000峰全14座登頂、北極から南極まで北・中・南米の人力縦断、熱気球による太平洋横断挑戦など、などさまざまな経験を重ねる中で石川さんはどのような冒険観を得たのか? 関野さんが迫ります。
「僕は冒険家ではない――肉を切らせて骨を断つところまで突っ込めないから」

関野吉晴/せきの・よしはる
1949年東京都生まれ。探検家、医師、武蔵野美術大学名誉教授(文化人類学)。一橋大学在学中に探検部を創設し、アマゾン川源流などでの長期滞在、「グレートジャーニー」、日本列島にやってきた人びとのルートを辿る「新グレートジャーニー」などの探検を行なう。
石川直樹/いしかわ・なおき
1977年東京都生まれ。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、ヒマラヤの高峰、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている写真家。2011年、『CORONA』により土門拳賞、2020年、『EVEREST』、『まれびと』により日本写真協会賞作家賞を受賞。
死を覚悟した熱気球太平洋横断
関野 2001年、石川さんはエベレストに登頂。7大陸最高峰登頂の最年少記録(当時)でしたね。その次は一転、熱気球による太平洋横断に挑戦します。
石川 熱気球冒険家の神田道夫さんと出会い、2004年に挑戦しました。自分たちで布を縫い合わせて巨大な気球を作り、ゴンドラはビルの屋上にある水タンクを利用し、魚屋にあるような発泡スチロールをゴンドラの四方につけて着水時の浮力にするなど手作り感にあふれていました。
関野 ゴンドラは空気を通さない気密室なのですか?
石川 気密室ではありませんでした。ですから、地上から酸素ボンベで酸素を吸っていました。途中6000mとかから吸い始めても遅くて、意識を失ってしまうそうなんです。そんな手作りの熱気球で高度8000m以上に達し、ジェット気流に乗って飛ぶなんて、今やれといわれてもちょっとできません。
実際そのときもトラブルがあり、ハワイの手前で不時着水しました。たまたま通りかかったロサンゼルス行きの貨物船が救難信号をキャッチして救助してくれたのですが、ゴンドラ内は胸ぐらいまで浸水してきて死を覚悟しました。
関野 飛んでいるときは怖くない?
石川 陸地の上を飛んでるときは、ゆっくり降りれば助かるだろうと思えて恐怖はあまりなかったんです。でも、海の上に気球が出ると、本当に足がすくむような感じでどこに落ちてもどんなことをしても絶対助からないぞと感じました。ものすごい怖かったです。
関野 だから、2度目、3度目は断わったんですね。
石川 断わりました。怖かったですし、あのような手作りの熱気球では厳しいと思ったので。でも神田さんは熱気球を改良すれば今度は必ず成功すると信じていました。なにしろ、救助された直後、死の恐怖の記憶がまだ鮮明だったときから、次の挑戦の計画や成功するためにはどうしたらいいかをひたすら僕に話しかけてきたぐらいですから。
「肉を切らせて骨を断つ」ということばがありますが、普通の人なら肉を切られたら痛いから退いてしまうところを、神田さんは肉を切られてもガンガン前に突っ込んでいける人でした。結局、2008年の挑戦では神田さんはひとりで飛び、行方不明になってしまいました。
関野 石川さんは著書『最後の冒険家』の中で、神田さんこそこれぞ冒険家という人だったと書いています。石川さんが考える冒険家の定義とはどのようなものなのですか?
石川 神田さんのように、真に生きるためには死をも厭わず、死のリスクを冒して進んでいく人が冒険家だと僕は考えています。だから僕は、自分は冒険家ではないとずっといい続けてきました。なぜなら、そうやって肉を切らせて骨を断つところまで自分は到底行けてないからです。僕はそこまで突っ込めないんですよね。
関野 どこまでだったら突っ込めますか? 私だったら助かる確率が半分以下だったらやらないですが、石川さんはどうですか?
石川 やらないですね。僕も半分以下ならやりません。
この続きは、発売中のBE-PAL1月号に掲載!
公式YouTubeで対談の一部を配信中!
以下の動画で、誌面に掲載しきれなかったこぼれ話をお楽しみください。