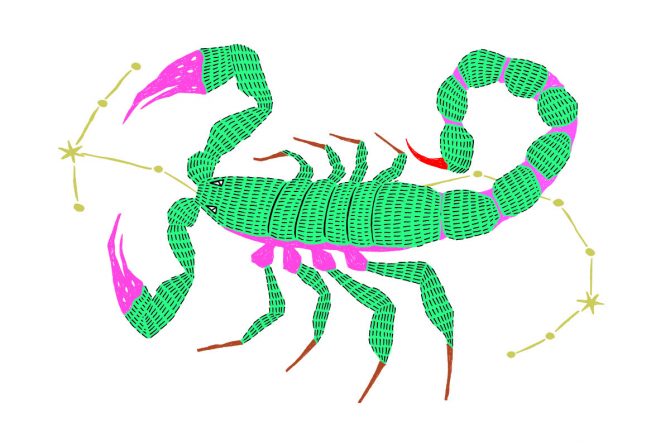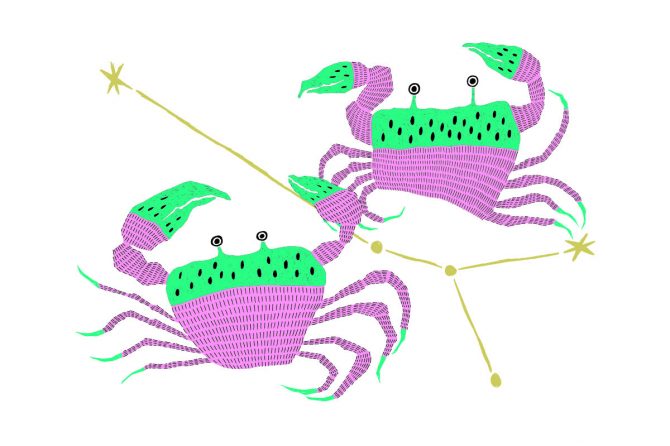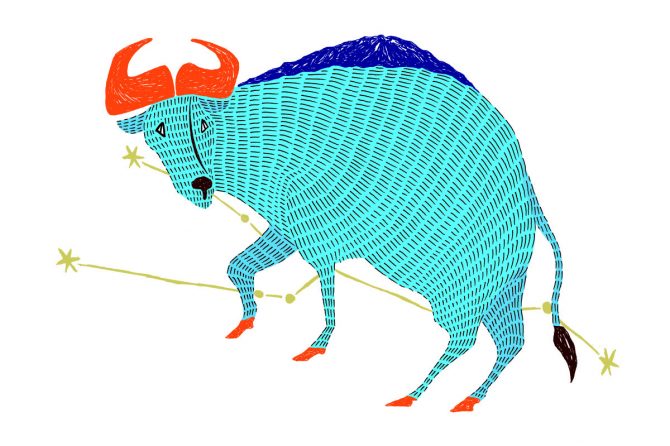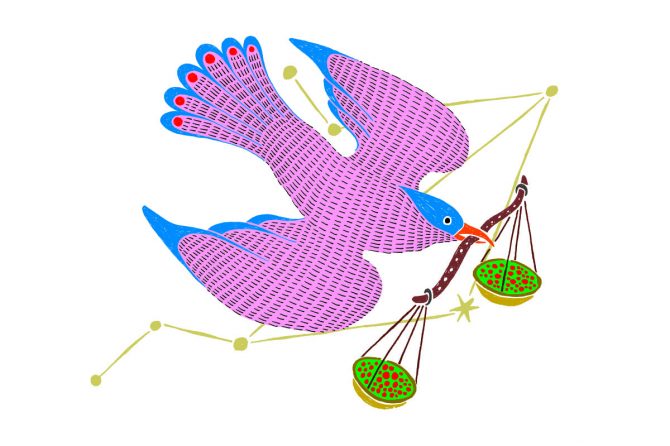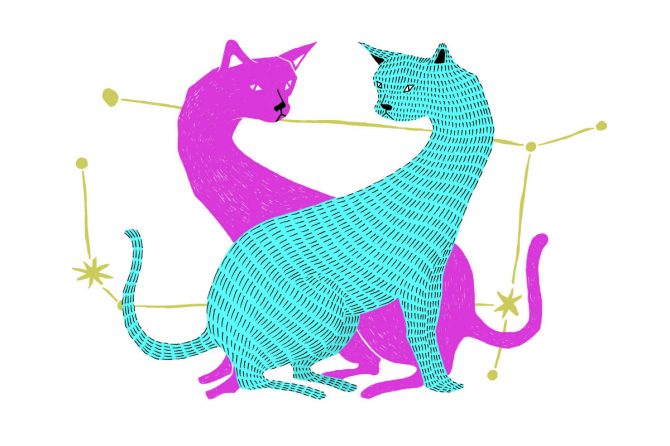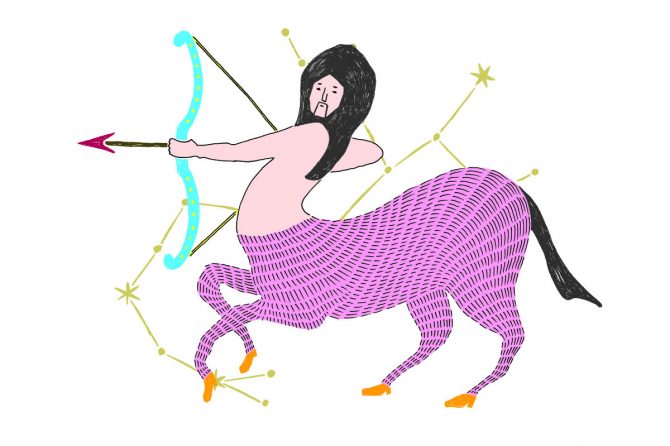文鳥社が目指すデザイン的な思考を体現したものが文鳥文庫といえる。
文鳥文庫は、すべて16ページ以内の短編だ。
製本されてはおらず、蛇腹の紙に各小説が印刷されている。
そもそもは大宰治『走れメロス』が16ページしかないという話を、
知り合いの博報堂のデザイナー、柴田賢蔵さんに話していたことがきっかけだった。
「まさにデザイナー的発想だなと思うんですけど、
文庫サイズで16ページというとすぐに“A3の紙の表裏か”というんです。
だから最初は『走れメロス』をA3の表裏に印刷して発売するっていう発想が生まれました。
みんなが普段、普通に使っているA3の紙に、『走れメロス』が収まっているというのは、
象徴的でおもしろいかなと思って。
でもやってみると、少し文字が詰まった印象になってしまって、圧力を感じてしまうので、
結局、蛇腹に落ち着きました」
この発想は、出版社の人間からはなかなか生まれないものだろう。
「“本というずっと形が変わっていないものでも、
違う形にしていい”というのが主張としては一番大きいですね。
出版社の人は、きっと本の中味のことはすごく考えているけど、体裁を疑ったことはないと思います。
数ページしかない短編なので、何本かまとめて『短編集』として売っていることが多いので、
そもそもバラバラに売るということもあまり考えたことがないと思う。
前提を疑ったり、まだまだ適した形があるのではないかと追求することが、デザインの始まりだと思います」
たしかに蛇腹や封筒はありふれたもの。
最先端技術が使われているわけではないし、小説自体も古い作品が中心になっている。
それでもあたらしいものは生み出せる。
これを牧野さんは“何の変哲もないイノベーション”だという。
「実際、大したことはしてないわけですよ。
あたらしくないのに、あたらしがってくれる。
イノベーションというと、斬新で大きく変化するようなイメージがありますが、
生活のなかから生まれる“何の変哲もないイノベーション”を起こしていきたいと思っています」

100年後に残る名作は、ネット上にあり!?
牧野さんは、子どものころからの文学少年というわけではなかった。
読書を好きになったのは、大学時代。それはある作品ともリンクしていた。
「大学がつまらなくて、現実逃避で小説を読み始めたんです。
特に村上春樹さんに、はまりました。
“早稲田大学で、学校がつまらない”というのは、『ノルウェイの森』と同じ状況なんです(笑)。
するとやはり村上春樹さんに走るんですね。
早稲田大学の生協の書店は、卒業生である村上春樹さんばかりだから、片っ端から読みました。
そのなかから『四月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて』
という短編を出したいと思ったんです」
現在、文鳥文庫として第1弾、第2弾を合わせて、16作品を発売している。
もちろん16ページ以内という大前提のほかに、文鳥文庫なりのセレクト基準はある。
それは牧野さんが考える小説の深遠なる世界だ。
「僕が文学を語れる立場にはありませんが、文章の密度と深さがある作品を発売していきたい。
16ページなのに読み込めない深さがあったり、世界観が詰まっているものが好きです。
特に長く受け継がれてきた作品たちは、やはりいい作品が多いなと思います」
宮沢賢治、太宰治、芥川龍之介、坂口安吾、谷崎潤一郎、三島由紀夫…。
現状では、大正から昭和にかけての作品が多い。
「これからは現代作家も増やしていきたいです。
しかし偏見かもしれませんが、これまで発売した作品の時代背景と現代とでは、
孤独の質が違うように思います。
宮沢賢治のように岩手の雪の深いなかで閉じこもって書いている文章と、
隣にスマホがあって、いつ誰とでも連絡がとれる世の中で書いている文章とでは、
質が変わってくるはずです」
たしかに書かれている時代や環境は常に変化するもの。
ただし、社会に対する反動や対抗心が創作意欲につながっていくというモチベーションは、
変わらないかもしれない。そういう意味では現代がもつ“闇と病み”は、どこにあるか。
「もしかしたら“2ちゃんねる文学”みたいなものが、100年後に評価されているかもしれませんよね。
実際、それで泣いたことありますから。いつか、名無し作家の企画をやってみたいんですよ。
どこの誰が書いたのかわからないけど名文みたいな」
本の体裁を変えることで、内容もウィットに富んだものが増えていく。
デザイン思考で本を考えてみれば、古い新しいは関係なく、
まだまだ色々な可能性が文鳥文庫にはありそうだ。
文=大草朋宏