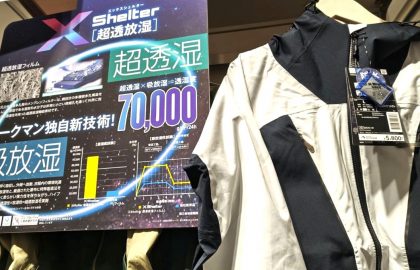ラロトンガ島は、南太平洋に浮かぶ周囲32キロの小さな島である。島の真ん中に山がある火山島で、そのまわりをサンゴ礁に囲まれている。ラロトンガ島のラグーンはそれほど広くはないが、それでもサンゴ礁が発達しており、その内側と外側で多くの海の生物を見ることができる。
島に滞在していると、嫌でも毎日海を眺めることになる。日差しは鋭く、その光を受けて海は刻々と表情を変えながら、さまざまな青に輝いている。冬にはザトウクジラが子育てのためにやってくるのだが、島の北側にあるブラックロックの高台からその雄大な背中が水面に現れては消えていくのを見ていると、クジラが見ている世界をこの眼で見てみたいと感じてしまう。
ラロトンガ島は基本的に南東からの風が一年を通じて吹くため、島の南東側には波が打ち寄せ、サンゴ礁のリーフが発達しにくい。反対に北西側は島影になるため、波の影響を受けることなく広くて浅いラグーンが広がっている。
滞在中、さまざまな場所でスノーケリングをしたが、ダイブセンター前と呼ばれるポイントが、一番魚影が濃く種類が多い。
フィンとマスクを付け、海に飛び込む。すると、たった一歩水面を越えただけで、陸上とは全く違う原理で成り立っている世界がそこにある。上げ潮の時に海に入ると、外洋からの澄んで冷たい水が入ってきて、透明度があがる。水面をたゆたう波が水底の白砂に影を生み出し、ところどころサンゴの根が点在する。水深は1〜2mほどしかないが、エダサンゴやテーブルサンゴの仲間が太陽光目指して伸びる。サンゴのまわりにはデバスズメダイが水に溶け込むかのように水色の群れをなし、アオブダイがサンゴを囓りながら行進する。ふと気配を感じて振り返ると、外洋から入り込んできた大型のカスミアジが悠々と泳ぎ、シマハギが群れをなして揺らめいている。熱帯のサンゴ礁をイメージするとき、多くの人が頭に思い浮かぶような光景そのままが、ラグーンに溢れているのだ。少しだけのつもりで泳いでいても、いつもその時間が長くなってしまう。気がつけば2時間以上も泳ぎ続けていたこともある。
ある日、船に乗って外洋の海を潜る機会があった。アバルア港から出港し、島の北側にあるダイブポイントに飛び込むと、無数の気泡が視界を奪った。やがてひとつまたひとつと泡は浮上していき、その先に海底が見渡せた。ラグーンとは違って質感のある澄んだ青の世界が広がり、その向かう側にサンゴが群生している。ハマサンゴやハナヤサイサンゴがうねるように重なり合っては波打っている。ラグーンのなかの落ち着いた印象ではなく、もっと無骨で荒々しい。
ラロトンガ島はサイクロンの進路から外れており、滅多に直撃することはない。それに加えて、排他的経済水域内のすべてが保護区に指定されているクック諸島の海は、原始そのもの。人の眼に触れず、何千年、何万年と繰り返されてきた自然の営みが眼前に広がる。無数のサンゴが折り重なる様子は、まるで自然の時間の積み重ねを眺めているようである。
ポイントは外洋に向かってなだらかに傾斜して深くなっていき、やがてドロップオフとなっている。そのエッジに潮流があたり、魚が集まる。ホソカマスが群れ、マダラトビエが戦隊を組んで飛来する。水底には巨大なアオウミガメが横たわり、シルバーチップシャークが眠る。
ダイビングを終え、水面に顔を出すと、海越しに島の最高峰であるテマンガ山が眼に入った。それはまるで海からそのまま山がそそり立つように見えた。ダイビングを終えて水面に戻って来ると、まるで島の体内から戻ってきたような気がした。
ラロトンガ島では人は海と山の間に、伝統と文化を重んじながら生きている。人、海、山。この島ではそれらが一体となって存在している。この島を訪れる者は、その島の一部となるのである。そして、それは大いなる存在に抱かれているという不思議な安心感を与えてくれるのだった。
次回へ続く。
写真・文 竹沢うるま
(プロフィール)1977年生まれ。写真家。
ダイビング雑誌のスタッフフォトグラファーとして水中撮影を専門とし、2004年よりフリーランスとなり写真家としての活動を本格的に開始。2010年〜2012年にかけて、1021日103カ国を巡る旅を敢行。写真集「Walkabout」(小学館)と対になる旅行記「The Songlines」(小学館)を発表。2014年第三回日経ナショナルジオグラフィック写真賞受賞し、2015年に開催されたニューヨークでの個展は多くのメディアに取り上げられ現地で評価されるなど国内外で写真集や写真展を通じて作品発表。世界各地を旅しながら撮影をし、訪れた国と地域は145を越す。近著にチベット文化圏をテーマとした写真集「Kor La」(小学館)や「旅情熱帯夜」(実業之日本社)がある。